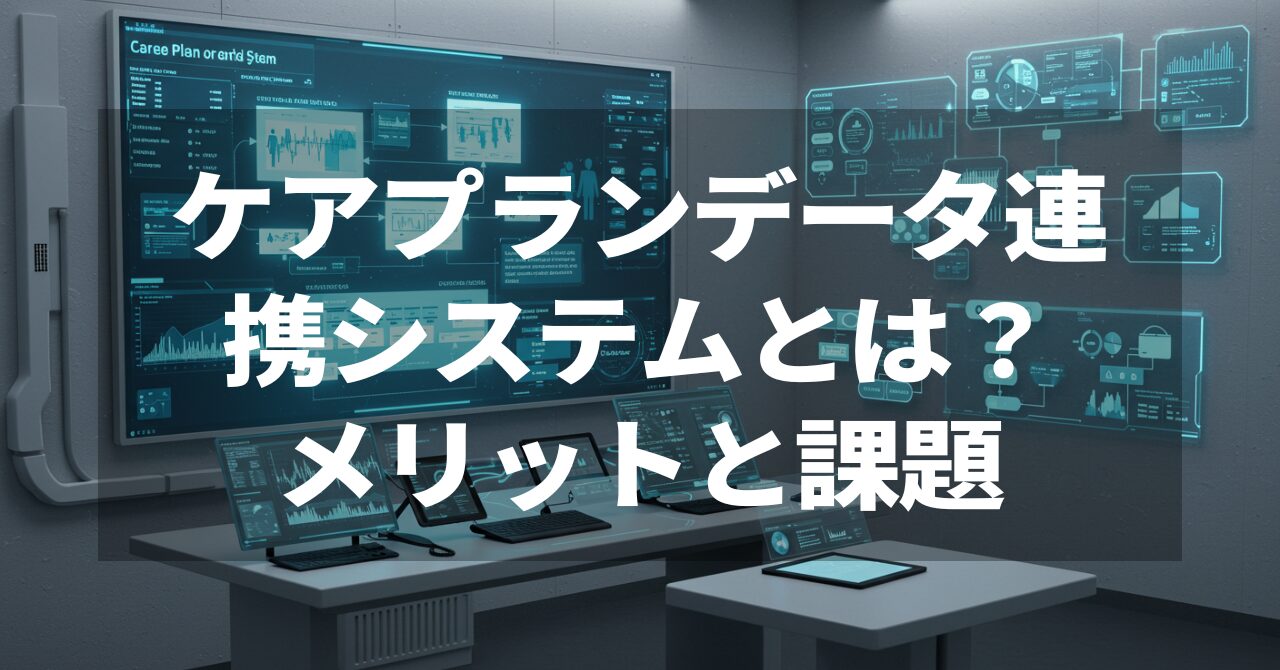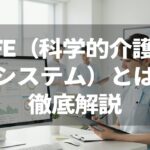介護保険制度では、利用者一人ひとりの状態やニーズを踏まえた「ケアプラン(居宅サービス計画書)」を作成し、サービス提供事業所や自治体(市町村)、国保連合会などが関わりながらケアを行います。しかし、紙ベースの書類管理では転記作業や郵送コストなど多くの非効率が生じることも事実。そこで注目されているのが、ケアプランを電子化し、関係者間でデータをやり取りする「ケアプランデータ連携システム」です。本記事では、このシステムの概要・導入メリット・居宅介護支援費Ⅱの加算要件との関係などを解説しながら、今後の展望を考察していきます。
ケアプランデータ連携システムの概要
ケアプランデータ連携システムとは、ケアマネジャーが作成した居宅サービス計画書やサービス提供票などを電子化し、効率的かつ安全に共有するための仕組みです。従来の紙ベースでは郵送やFAXに頼る場面も多く、タイムラグが発生しがちでしたが、このシステムを利用することで大幅にスピードアップを図ることができます。
紙から電子へ:情報共有の効率化
紙のやり取りでは、誤送・転記ミス・重複入力のリスクがつきまといます。データ連携システムでは、プランの変更などが発生した時点で電子的に即座に修正し、共有先に通知できるため、必要なサービスの提供をスピーディーに進められます。
民間システムだけで完結するケース
一部では「国保中央会のシステムを使わなければ電子連携は不可能」という誤解があるものの、実際には民間ベンダーの介護ソフトでも独自のクラウドサービスを使い、事業所間でデータをやり取りしている事例があります。ただし、後述する加算要件に適合するかどうかは別問題となります。
導入のメリットと主な機能
ケアプランデータ連携システムを導入する最大のメリットは、情報共有に伴う手間とコストを大幅に削減できる点です。ここでは、代表的な機能・利点を整理してみます。
業務効率化と情報の一元管理
- 重複入力の減少 紙ベースで何度も同じ内容を転記する手間が減るため、スタッフの業務効率がアップします。
- 利用者情報の集約 ケアプラン、利用者の基本情報、サービス提供履歴などを一元管理できるので、連絡漏れや内容の重複・誤りが起こりにくくなります。
セキュリティと正確性の向上
- 電子証明書や暗号化通信 個人情報保護が求められる介護現場でも、安全性を確保しながらデータを送受信可能。
- リアルタイム更新 利用者の状態変化があれば、すぐに計画を修正して反映でき、現場での迅速な意思決定を支えます。
居宅介護支援費Ⅱと加算要件
ケアプランデータ連携システムと密接に関係するのが、ケアマネジャーが算定できる居宅介護支援費Ⅱの加算要件です。ここを理解しておくと、制度上どのようなシステム活用が求められているのかが見えてきます。
加算要件におけるシステム活用の必須化
居宅介護支援費Ⅱを算定するためには、厚生労働省が示す「ケアプランデータ連携システム」を活用することが必須とされています。これに該当しないシステムで電子化を行っていても、現行制度上は加算要件を満たすことにはなりません。
将来的な他システムの認可
ただし、同等の機能・セキュリティを備えた他システムについては、今後認められる方向で話が進んでおり、具体的な精査が進行中です。民間ソフトウェアを中心に独自で連携を完結させている事業所にとっては、制度改正によって選択肢が広がる可能性もあります。
国保中央会システムと民間ベンダーの違い
システム選定の際、「国保中央会のシステム」と「民間ベンダーのシステム」のどちらを使うべきか迷う事業所も少なくありません。ここでは、それぞれの特徴を簡単に比較してみます。
国保中央会のシステム
- 公的信頼性の高さ 全国統一仕様で運用しており、利用時点で居宅介護支援費Ⅱの加算要件を満たす形になっている。
- 費用と運用ルール ライセンス料や電子証明書、端末ごとの履歴管理など、導入コストや運用の手間がかかる。
民間ベンダーのシステム
- 操作性や機能面が充実 請求業務や記録管理を一括で行えるソフトも多く、現場での利便性が高い。
- 現時点での加算要件対応は不透明 今後の制度改正次第で、認可されるシステムが増える可能性がある。
導入に伴う注意点・課題
システム導入に踏み切っても、現場での運用や周囲との連携がうまくいかなければ意味がありません。ここでは、よく指摘される課題を整理してみましょう。
双方が導入しなければ成立しない
介護業務はケアマネだけで完結するものではなく、通所介護・訪問介護など複数のサービス提供事業所が連携して成り立ちます。片方だけがデータ連携システムを導入しても、相手が紙ベースのままだと効率化の恩恵は限定的です。
端末ごとの履歴管理と運用ルール
とくに国保中央会のシステムを使う場合、1事業所1台のPC運用が推奨されるケースがあります。異なる端末で操作すると、送受信履歴が端末ごとに分散してしまい、トラブルの原因となるため注意が必要です。
代替手段や他のツール
ケアプランデータ連携システムを活用しないまでも、ある程度の電子化を実現する方法はいくつかあります。ここでは代表的な代替ツールを紹介します。
ケアぽす
厚生労働省が定める「標準仕様(データフォーマット)」に対応したソフト同士であれば、CSVやPDFファイルを介してやり取りが可能です。双方が「ケアぽす」を導入している必要はありますが、比較的導入ハードルが低めとされています。
カイポケ
カイポケ会員の居宅介護支援事業所が、非会員のサービス事業所へPDFファイルを一括送信できる仕組みを提供。カイポケ同士であればサービス提供票や実績の送受信をさらにスムーズに行えます。
オンラインストレージやインターネットFAX
GoogleドライブやOneDriveなどのオンラインストレージを使い、CSVやPDFファイルをパスワード付きで共有する運用もあるほか、紙でしか対応できない事業所にはインターネットFAXを利用するなど、柔軟な組み合わせが考えられます。
普及状況と今後の展望
一都三県(東京・神奈川・千葉・埼玉)の導入率を概算で見ると、まだ5%程度との声もあり、全体的に普及は進んでいないのが現状です。導入コストや周辺事業所のITリテラシーなど、さまざまな要因が影響しています。
しかし、国のデジタル化推進(DX)政策や介護報酬加算との連動もあり、今後は徐々に導入が拡大するとみられています。加えて、民間システムでも同等機能が認められる可能性が出てくれば、一気に普及が加速する可能性も否定できません。
まとめ
ケアプランデータ連携システムは、介護現場の情報共有を効率化し、利用者へのサービス提供をスピーディーにするための重要なツールです。ただし、居宅介護支援費Ⅱの加算を得るためには、現行制度上「ケアプランデータ連携システム」として認められたものを利用する必要がある点が最大の特徴といえます。
今後、同等の機能をもつ他システムの認可が進めば、民間ベンダー独自の仕組みであっても加算要件に適合する余地が生まれるでしょう。現場での業務効率やスタッフの教育コスト、連携先の導入状況などを慎重に見極めながら、自事業所に最適なスタイルを選択していくことが求められます。
参考リンク
本記事は2025年1月時点で公表されている情報をもとに執筆しています。実際にシステムを導入する際は、最新の厚生労働省通知や保険者への確認を行い、制度改正の動向を注視してください。本記事は2025年1月時点で公表されている情報をもとに執筆しています。実際にシステムを導入する際は、最新の厚生労働省通知や保険者への確認を行い、制度改正の動向を注視してください。