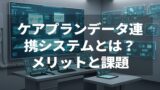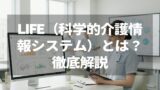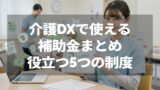はじめに~なぜ介護業界にDXが求められるのか
高齢化が進む日本において、介護サービスへの需要は今後もますます高まると予想されています。しかし、それに対応するスタッフは慢性的に不足しており、利用者が増加し続ける一方で介護現場の負担は深刻化しているのが現状です。特に小規模な事業所では、人手不足ゆえに通常業務だけでも手一杯で、新しい取り組みに着手する余裕がないと感じるケースが多く見受けられます。
それでもなお、介護業界にDX(デジタルトランスフォーメーション)が求められるのには明確な理由があります。アナログ作業の多い介護現場では、手書きの記録や紙ベースの帳票管理が日常的に行われていますが、これらは業務効率を大きく下げる要因になるからです。
加えて、情報共有が十分にデジタル化されていないため、職員同士が連絡ミスを起こしたり、重要な情報の抜け漏れが生じたりといったトラブルが起こりやすくなっています。
さらに、働くスタッフの立場から見れば、時間と体力を奪われるのは書類処理や重複入力だけではありません。
紙資料の管理や過重労働が離職の引き金になり、せっかく採用した職員が現場を去ってしまうことも珍しくないのです。
こうした問題を解決する糸口として、DXによる効率化や情報共有の高度化が注目を浴びています。
ポイント
- 高齢化社会による利用者数の増加
- スタッフ不足と業務過多
- 紙ベースの記録・帳票管理による負担増
- 離職率低下・人材定着のためにもDXが鍵になる
介護DXとは? その定義と狙い
介護DXの定義
介護DXとは、業務効率化やケアの質向上を目指し、現場のプロセスやサービスをデジタル技術によって抜本的に変革することです。
一般企業におけるDXでは、AIやIoTを導入してビジネスモデルを刷新する例が多いですが、介護業界においては、介護記録の電子化やケアプランのデジタル連携など、現場の日々の業務を根本から見直す側面がより強くなります。
一般的なDXと介護DXの違い
多くの業界でDXが進められていますが、介護の現場には特有の事情があります。日々のケアが対人サービスであることや、紙への手書き記録が長年当たり前とされてきた文化が根強いことなど、単純に「ITツールを入れればいい」という発想だけでは十分に成果が出ません。
- 現場特有のコミュニケーション 介護職員は利用者との対話や手厚いサポートを通じてニーズを捉えています。そのため、単にデータのやりとりをデジタル化するだけでなく、現場のスタッフ同士の言語化しにくい情報交換までカバーする仕組みづくりが重要です。
- ケア記録の重要性 利用者のバイタルや身体状況、認知面の変化など、日々蓄積される記録の質がサービス向上に直結します。介護DXでは、このケア記録の電子化やデータ分析を進めることで、より適切な判断やケアプランの策定を支援する効果が期待できます。
- アナログ文化の置き換え 介護現場には長年蓄積された紙ベースの帳票管理や慣習が多く、これをいきなり完全電子化しようとしても抵抗が生じる可能性があります。小規模事業所では特に、現場スタッフの多くが「紙のほうが安心」と考えていることもあり、段階的なアプローチが必須です。
介護DXの目的
- 業務削減 記録入力や報告書作成の自動化を図り、重複入力や転記作業を減らすことで、スタッフの負担を軽減します。省力化によって余裕が生まれれば、より利用者と向き合う時間を確保できるでしょう。
- データ活用によるケアの最適化 利用者状況を即時に共有し、必要なときに必要な情報を閲覧できるようにすることで、ケアプランの質とスピードが向上します。要介護度変化への迅速な対応や、複数スタッフ間の情報連携が円滑になる点も大きなメリットです。
小規模事業所の視点
人材も少なく、紙ベースの情報管理に慣れきっていると、最初は導入コストやスタッフ教育へのハードルを感じるでしょう。それでも小さく始めてみることで、最終的には大きな時間短縮やケアの質向上につながる可能性があります。
生産性向上とDX
DXの先にある「生産性向上」
DXと聞くとITツールの導入ばかりがクローズアップされがちですが、その本質は「生産性をいかに高めるか」という点にあります。介護業界における生産性向上には、主に以下の2方向があります。
- 介護サービスの質の向上 見守りツールや介護ロボットを導入して利用者の安全を確保し、センサー技術の活用によって状態変化を早期に察知することでケアの質を高めることが可能です。特に、小規模な事業所でも気軽に導入しやすい見守りセンサーは、利用者の転倒や体調不良を早期に把握できるため、スタッフの負担を減らしつつサービスレベルを上げられる事例が増えています。
- 職員の負担軽減(人材の定着・確保) 夜間巡視や記録作業に費やしていた時間を削減できれば、スタッフに余裕が生まれ、新人教育やチームでの連携に注力しやすくなります。離職率の改善にも寄与し、組織としての安定性を高める効果も期待できるでしょう。
業務プロセスを整える重要性
ただし、どんなに優れたツールやロボットを導入しても、現場の業務フローが属人的で不明瞭なままでは効果を得にくいものです。
特に、紙への記録や担当者ごとに異なる運用ルールが入り乱れた状態では、せっかくのデジタル化も混乱を生む可能性があります。
業務プロセスの棚卸し
まずは、現場でどの業務に無駄や手戻りが多いかを洗い出し、改善策を検討します。
- 「日報作成に毎日1時間かかっている」
- 「記録ミスや連絡漏れが原因で利用者対応が遅れることがある」
といった具体的な課題を明確にし、そこから優先的に対策を立てることが肝心です。
標準化・マニュアル化
次に、誰が担当しても同じ品質と手順で業務をこなせるようにルールやマニュアルを整備します。
特に夜勤や休日の人員が少ないときでも混乱が起きないよう、必要書類の記入方法やオンラインフォームへの入力手順などを統一しておくと、スタッフが変わっても業務を引き継ぎやすくなります。
デジタル化しやすいフローへの改善
これらのプロセス整理のうえで、紙書類中心だった部分を少しずつタブレット入力へ移行するなど、デジタル化への移行を進めていきます。
最初からすべてをオンライン化しようとすると抵抗が大きいため、小規模事業所ほど「簡易なツール→スタッフが慣れる→徐々に拡張」という段階的アプローチが有効です。
具体的な介護DXの領域とソリューション例
介護DXという言葉を聞くと、真っ先に「記録の電子化」をイメージする方が多いかもしれません。しかし、実際にはさまざまな領域でデジタル技術が活用され、業務効率やケアの質向上に貢献しています。
ここでは代表的な分野と取り組み事例をいくつか紹介します。
介護記録・帳票管理のデジタル化
クラウド型介護記録ソフト
介護記録・帳票管理のデジタル化は、DXの中でも特に導入しやすい分野です。
クラウド型の介護記録ソフトを使えば、タブレットやパソコンから利用者のバイタルや日々のケア内容を簡易入力でき、紙の二重記入やエクセルへの転記などを大幅に削減できます。
- メリット
- 紙資料の保管スペース削減
- 情報検索・集計の高速化
- スタッフ間のリアルタイム共有が容易
- 導入のポイント
- 現場スタッフの操作教育に時間をとる
- 段階的に紙から移行し、抵抗感を減らす
- 既存の業務プロセスを整理したうえでツールを選定する
AIを活用した文書自動作成
最近では、AI技術を用いて日報や報告書の下書きを自動生成できるサービスも登場しています。
スタッフは生成された文章を微調整したり加筆したりするだけで書類を完成できるため、事務負担を大幅に軽減できる可能性があります。
小規模事業所の場合、限られたスタッフが多岐にわたる帳票を作成しなければならないケースが多いため、こうした自動化機能があると非常に助かるでしょう。
AI・生成AIの活用
AIと一口にいっても、その活用方法は多岐にわたります。介護業界では、利用者データを分析して要介護度の変化を予測したり、スタッフ間の問い合わせに自動応答したりといった使い方が注目されています。
特に最近では、自然言語処理技術が進歩した「生成AI」(例:ChatGPTなど)が話題を集めており、ドキュメントのドラフト作成やFAQ対応などへも応用が広がりつつあります。
AIを使ったケア計画支援
利用者個々の疾患や身体状況、過去のケア履歴などを解析し、適切なケアプランを立案する補助をAIが行う仕組みも開発されています。
あくまで“補助”としての役割ですが、ケアマネジャーが膨大な情報を整理しやすくなるため、スピーディなプラン策定に寄与するでしょう。
よくある質問への自動応答
施設内のスタッフからの問い合わせや、利用者家族からの基本的な質問に対して、AIチャットボットが一次対応を行う事例もあります。
これにより、スタッフが電話や口頭説明に追われる時間を減らし、本来のケア業務に集中できるようになります。
ただし、あまりに機械的な応対にならないよう、対人コミュニケーションとのバランスが大切です。
IoT・センサー技術の導入
見守りセンサー
利用者の居室やベッドにセンサーを設置し、夜間や離床時の様子を把握できるようにする見守りシステムは、介護現場で急速に普及が進んでいる分野の一つです。
小規模なユニット型施設や在宅介護でも比較的導入しやすい機器が増えています。
- 効果
- 夜間の巡回回数を最適化し、スタッフの身体的負担を軽減
- 転倒や体調異変を早期発見し、重症化を防ぐ
- 介護記録ソフトと連携することで、自動でバイタルや動きのログを記録可能
バイタル測定デバイスとの連携
血圧や心拍数、体温などを自動でモニタリングできるデバイスを利用し、そのデータをクラウド上で一元管理する事例も増えています。
離れた場所にいる医師や管理者へ情報をリアルタイムに共有できるため、異変に対する対応が迅速になるだけでなく、不要な受診や往診を減らす効果も期待できます。
ロボット・パワーアシストスーツ
移乗介助ロボット
移乗介助ロボットは、利用者がベッドや車いす、トイレなどへ移動する際の身体的負担を大幅に軽減します。
特に腰を痛めがちな職員にとっては大きな助けとなり、腰痛対策や離職予防にも役立つでしょう。
パワーアシストスーツ
装着型のパワーアシストスーツは、スタッフ自身が装着し、腰や膝にかかる負担を軽減するタイプが主流です。機器導入にあたっては多少の初期コストやメンテナンスが必要になりますが、現場での身体的リスクを下げるうえでの効果は見逃せません。
小規模事業所でも、スタッフ数名が交代で使用する形で導入している例が少なくありません。
なお、介護ロボットやICTの具体的な種類、そしてそれぞれをどのように活用できるかについては、別の記事で詳しく解説しています。導入の判断材料や事例を知りたい方は、そちらもぜひご覧ください。
LIFE・ケアプランデータ連携システムなど主要システムの概要
介護現場におけるデジタル化を推進するため、国主導でさまざまなシステムが整備されています。その代表例がケアプランデータ連携システムとLIFE(科学的介護情報システム)です。
これらを正しく活用すれば、ケアプランの作成や評価、フィードバックの循環が効率よく行えるようになります。
ケアプランデータ連携システム
居宅サービス計画書を電子化し、ケアマネジャー、サービス事業所、市町村、国保連合会などが共同で利用できる仕組みを目指すシステムです。
本来であれば、紙ベースでやり取りしていたプランをオンラインで閲覧・更新できるため、連携のスピードと正確性が向上します。しかし実際には、導入率があまり高くないという課題もあり、「結局メールやFAXで送っている」という現場の声もしばしば聞かれます。
LIFE(科学的介護情報システム)
LIFEは、全国共通の指標を用いて利用者の状態やケア内容をデータとして蓄積し、フィードバックを施設側に提供することでケアの質を科学的に高めようとするシステムです。
PDCAサイクルに則った継続的なケアの改善が期待されますが、「フィードバックデータの精度や有用性に疑問がある」「事業所がうまく活用しきれていない」といった指摘もあるのが現状です。
ケアプランデータ連携システムとLIFEの詳細な仕組みや運用方法などは別の記事でより詳しくまとめています。 さらに深く知りたい方は、あわせてご参照いただければと思います。
実践的な導入ステップ
DX導入を成功させるには、明確なステップを踏んで進めることが重要です。何の準備もないままシステムを入れようとすると、スタッフが操作に戸惑って現場が混乱するだけで終わる恐れがあります。
現場課題の洗い出し
まずは、日々の業務のどこに一番時間がかかっているのか、どこでミスが起こりやすいのかを洗い出すことから始めます。
- 例1: 日報作成や記録の転記に毎日1時間以上かかり、サービス残業が当たり前になっている
- 例2: 紙資料の確認漏れが原因で、利用者への対応が遅れた経験がある
こうした具体的な課題を把握することで、「何を改善すれば効果が大きいのか」が見えてきます。
小規模なツール導入から試す
最初から包括的なシステムを入れようとしても、現場のスタッフが混乱し、逆に手間が増えるリスクがあります。まずは無料トライアル可能なクラウドソフトや、簡単な見守りセンサーなどをテスト導入し、効果や使い勝手を検証してみましょう。
特に小規模事業所では、一度に大きく変えるより「小さく導入→現場に慣らす→少しずつ拡大」の方が成功しやすい傾向があります。
スタッフ教育・定着支援
新たなシステムを導入する際は、操作マニュアルやオンライン勉強会の開催など、スタッフの教育が欠かせません。小規模な組織だからこそ、全員が同じ理解度になるようにフォローするのが容易であり、その分、定着もしやすくなります。
質問を受け付ける窓口を設けたり、定期的に振り返り会を行ったりして、導入後の不満やトラブルを早めに解消しましょう。
データ活用による改善サイクル
導入したシステムから得られるデータを活用し、作業時間の変化や記録ミスの件数などを数値で確認します。効果が実感できれば、ほかの業務(たとえばシフト作成や利用者満足度の追跡など)に応用して、DXの取り組みを広げていきます。
最初から完璧を目指す必要はありませんが、徐々に成功体験を積み重ねながら拡大することが肝心です。
DXツール導入の具体的な流れやチェックポイント、トラブルシューティングなどについては、別記事の「DXツール導入ガイド」でご紹介しています。実際にツールを選び、運用する際の手順を知りたい方は、ぜひご覧いただければと思います。
ICT導入効果
厚生労働省の調査や、各種補助事業の実績からも、ICT導入による具体的な効果が報告されています。
- 文書作成時間の短縮 記録・帳票の自動化によって印刷コストや記録ミスが減り、スタッフの残業が大幅に削減された例が多数みられます。
- 情報共有の容易化 夜間や緊急時の連絡がスムーズになり、利用者の異変に迅速対応できるようになったという声も多いです。
- 直接ケア・利用者コミュニケーション時間の増加 間接業務が減り、利用者と接する時間を増やせることで、サービス品質の向上や職員のやりがい向上にもつながります。
- 職員の意識変化・定着率向上 新たなツールや働き方の導入により、スタッフ同士で業務改善のアイデアを出し合う雰囲気が醸成され、離職率が下がった事例も報告されています。
特に小規模事業所の場合は、もともとの人員体制が限られているぶん、わずかな時短でも大きな恩恵を感じやすいという特徴があります。
成功事例・効果イメージ
介護ソフト導入による書類負担の削減(小規模事業所)
導入内容
ある訪問介護事業所では、手書きで行っていた利用者記録や日報をタブレット入力に変え、シンプルなクラウド型介護ソフトを導入しました。導入前は、スタッフが紙に記入した内容を事務担当がまとめ直す作業が日常的に発生していました。
結果
- 書類作成の手間が減り、1日あたり30分~1時間程度の時短に成功
- 小規模だからこそ、スタッフ全員が同じ画面を見られ、情報共有もスピードアップ
- 残業が大幅に減ったことで、スタッフの離職意欲が下がり、組織の安定につながった
ポイント
最初は「導入コストがかかるのでは」「操作が難しいのでは」という不安が根強かったものの、機能を最小限に絞ったソフトを選んだことでスタッフ間の混乱が最小化できました。
徐々に使い方を覚える中で、「紙でやっていた時よりも楽になった」という声が増え、導入効果が定着しやすくなりました。
生成AIでの日報作成サポート(デイサービス例)
導入内容
小規模のデイサービス事業所では、生成AIを活用して日報や記録の下書きを自動生成するシステムを取り入れました。利用者の名前や基本情報、注意点などをあらかじめ入力しておくと、AIが文章をまとめてくれる仕組みです。
結果
- 日報作成時間が月合計で30%以上削減
- スタッフが残業をせずに翌日の準備まで行えるようになり、疲労度が軽減
- 余った時間を利用者とのコミュニケーションや業務改善の提案に回すことができ、全体的な職場の雰囲気も向上
ポイント
AIが生成する文章を完全に鵜呑みにするのではなく、最終チェックを人間が行うことで品質を保っている点が重要でした。
自動化に対する抵抗感はあったものの、使ってみると意外と便利で、二重チェックを徹底すれば安全性も確保できると認識が変わったそうです。
補助金・支援制度の活用
介護事業所がDXを進める際にネックとなるのが、導入や運用にかかる費用や人手です。そこで、国や自治体が提供しているさまざまな補助金や支援制度の活用を検討すると良いでしょう。
主な補助金の例
- IT導入補助金 介護記録ソフトやコミュニケーションツールなどの導入にかかる費用を一部支援する制度で、小規模事業所でも比較的利用しやすいとされています。申請時に必要となる書類や要件は細かいため、行政窓口や支援団体と連携して進めることがポイントです。
- 介護ロボット導入支援事業費補助金 移乗支援ロボットや見守りセンサーなど、ロボット技術を用いた機器の導入をサポートする補助金です。身体的負担の軽減が見込まれる機器に対しては、国や自治体から手厚い支援が受けられる場合があります。
生産性向上推進体制加算
2024年度の介護報酬改定で新設された加算の一つで、介護ロボットやICT機器を使って生産性向上を図る事業所を評価する仕組みです。
- 加算(Ⅱ)
- 基本的な生産性向上の取り組みを行う事業所が対象
- 月あたり利用者1人につき10単位程度を加算
- 加算(Ⅰ)
- より高度な取り組みを行う事業所が対象
- 月あたり利用者1人につき100単位程度を加算
小規模事業所の場合、データ提出や会議開催などの要件を満たす手間はありますが、加算を取得できれば経営の安定化にもつながります。実際に導入を検討する際は、申請書の書き方や報告義務などをしっかり確認しておきましょう。
いずれの補助金・加算制度も、申請要件や必要書類・手順が細かく定められています。導入を検討する際は、行政窓口や支援機関、ベンダーと相談しながら進めるのがおすすめです。
なお、詳細な補助金情報については下記の記事で解説しているため、ぜひそちらをご参照ください。
政府主導の生産性向上施策の課題点
国や自治体による生産性向上の施策は、介護業界全体のDXを後押しするうえで大きな役割を果たしています。しかし、現場レベルでは以下のような課題が指摘されています。
- ケアプランデータ連携システムの導入率の低さ
- LIFEの導入はそこそこ進んでいるものの、ケアプランデータ連携システムに関しては費用がかかることや導入率の低さの問題(相手方も導入していなければ使えない)であまり普及が進んでおらず、「結局、紙ベースやメール添付が主流」という現状があります。
- LIFEのフィードバック活用の難しさ
- 全国規模のデータをフィードバックする仕組みは画期的ですが、実際の施設がそれをどのように活用すればよいのか分からなかったり、精度や実用性に疑問を持つ事業所も少なくありません。
- 相互連携が進まない業界エコシステム
- システムやベンダーごとに仕様が異なり、CSV出力やメール送信といった暫定対応に頼らざるを得ないケースが多いです。
これが結果的に「システム間のデータ交換がスムーズに行えない」というボトルネックを生んでいます。
- システムやベンダーごとに仕様が異なり、CSV出力やメール送信といった暫定対応に頼らざるを得ないケースが多いです。
- 「だからDXは無意味」というわけではない
- 制度面での課題はあるものの、現場レベルの部分的な導入だけでも十分に生産性向上は期待できます。
今後、業界全体のICT化が進めば連携や統一規格も整備され、データ活用の幅がますます広がるでしょう。
- 制度面での課題はあるものの、現場レベルの部分的な導入だけでも十分に生産性向上は期待できます。
失敗を避けるためのポイント
介護現場でDXを導入するときに起こりがちな失敗としてよく耳にするのが、「高機能なシステムを導入したものの、実際には使いこなせず混乱を招く」というケースです。
とりわけ、小規模事業所はスタッフが少なく、導入そのものに割ける時間や人手が限られているため、せっかく購入したツールが「宝の持ち腐れ」になってしまう事態も起こりがちです。
ここでは、そうした失敗を避け、DXを着実に定着させるためのポイントを解説します。
過度な高機能に走らず、現場に合ったツールを選ぶ
いきなり多機能なシステムを導入すると、操作が複雑でスタッフ全員が使いこなせないというリスクがあります。特に小規模事業所では、日常業務に追われる中で新しいツールを学ぶ余裕がほとんどありません。
大事なのは、現場が本当に必要としている機能だけを満たすシンプルなシステムを見極め、そこから少しずつステップアップすることです。
高額なシステムが必ずしも現場にフィットするとは限りません。
導入前には、職員がどのように使うのか、どんな操作フローになるのかを具体的にイメージし、デモやトライアル期間を活用して十分に確認することが重要です。
小さな成功体験を重ねる段階的アプローチ
多くの失敗事例を振り返ると、「紙ベースの運用を一気にすべて電子化しようとして挫折した」というケースが目立ちます。
たとえば、まずは記録業務だけを簡易デジタル化してみる、あるいは一部分野のロボット導入に絞って導入効果を検証してみるなど、小さく始めることが成功のカギです。
スタッフが「これなら使いこなせる」「手間が減って便利だ」と実感すれば、次のステップに移行するときの抵抗も少なくなります。
段階的に導入範囲を広げながら、小さな成功体験を積み重ねていくのが、スムーズなDX定着の近道です。
スタッフの声を積極的に拾い上げ、柔軟に修正する
DXは最終的に現場のスタッフが運用しなければ意味がありません。新システムを導入しても、スタッフが「使いにくい」「何のためにやっているのかわからない」と感じてしまうと、現場に根付かず形骸化してしまいます。
そこで大切なのが、導入後も定期的に現場の声を吸い上げる仕組みをつくることです。
たとえばオンラインや対面での勉強会を開き、「ここが使いにくい」「こんな機能が欲しい」といった意見をすぐにフィードバックとして反映するようにします。
小規模事業所ならではのメリットとして、スタッフ全員とこまめに会話ができる点を活かし、改善を続けることで、トラブルを早期に解消できるでしょう。
現実的な計画を立て、完璧を求めすぎない
また、「国のシステムと連携して活用したい」「補助金を最大限活用したい」といった理想が先行すると、導入プロセスが複雑になり、かえって動き出せなくなる恐れもあります。
特に小規模事業所は、システム関連の担当者を専任で置くことが難しいため、あまりに大きな計画を描きすぎると途中で頓挫するリスクが高まります。
まずはできる範囲から着手し、徐々に連携や機能拡張を図るという柔軟なスタンスで進めることをおすすめします。国や自治体の支援策が今後拡充され、業界全体のICT化が進むにつれ、追加で取り組めることが自然と増えていくはずです。
このように、DX導入で失敗しないためには、「必要以上に高機能なシステムに飛びつかないこと」「現場で小さな成功を重ねながら段階的に進めること」「スタッフの声に耳を傾け、適宜修正を行うこと」「身の丈に合った計画を立てること」が大切です。
最初から完璧を目指すよりも、少しずつ改善を重ねる姿勢で取り組むほうが、最終的には現場にしっかり根付き、介護の質と生産性の向上につながるでしょう。
まとめ〜DXで介護現場を「本来のケア」に集中できる環境へ
DXは単なるIT導入ではなく、介護現場の業務プロセスを見直し、人と技術を組み合わせて最適なケアを提供するための手段です。紙書類やアナログな作業を少しずつデジタルに置き換えていくだけでも、日々の負担が軽減され、スタッフが利用者に向き合う時間を増やせるというメリットがあります。
特に人員やリソースが限られている小規模事業所こそ、段階的な導入とスタッフ教育を丁寧に行うことで、大きな成果を得られる可能性があります。自社の課題を洗い出し、解決策として適したツールを少しずつ試し、効果を実感しながら運用を拡大する――この積み重ねが、結果として“本来のケア”に集中できる理想の環境づくりにつながるはずです。
今後、国主導システムの連携強化やICT技術の進歩がさらに進めば、ケアプランの作成やデータの相互活用がよりシームレスに行える未来も見えてきます。デジタル化によってスタッフの負担を軽減し、利用者一人ひとりにより手厚く目を配れるようになること――これこそが、介護DXの目指す最終的なゴールといえるでしょう。
本記事のポイント
- 小規模事業所だからこそ、段階的なDX導入が効果的
- 補助金や加算制度を活用してコスト面の不安をカバー
- 業務効率化によって利用者とのコミュニケーション時間を創出
- 将来的には業界全体の連携強化で、よりスムーズなケアが実現
少しずつでも前に進むことが、介護業界の未来をより明るくする大きな一歩となるはずです。ぜひ、できるところからDXを取り入れ、貴重なスタッフの力を最大限に引き出しながら、利用者にとっても働く人にとっても優しい介護現場を築いていきましょう。